
病原体媒介節足動物との出会い
奥田:
嘉糠先生は東京大学の獣医学科を卒業された後に、大阪大学や理化学研究所でアポトーシスの研究をされていたそうですが、現在のお仕事に至ったきっかけや背景を教えてください。
嘉糠:
大学院で偶然、病原体媒介節足動物という概念を知った時に、虫が病気を運ぶということにそれはもう興奮して、運命的に「自分はこれをやるんだ」と思いました。「病気があって、感染症があって、それが虫によって運ばれる」というそのプロセスを知った瞬間に、これをやりたいと思ったんですよ。
奥田:
その当時の心境をもう少し詳しく教えていただけますか。
嘉糠:
僕の座右の銘は「好きこそものの上手なれ」です。好きだったら何でもうまくいく。その「好き」とは何かというと、詰まるところ、何か知った時、コトが起きた時に、夢中になれるかだけです。アドレナリンやドーパミンが出て、モチベーションが上がって行動力に繋がると、辛いことでも乗り越えられます。同じ事象に出会っても、夢中になる人もいれば、ならない人もいます。自分がどういったことに心を突き動かされるかは、突き詰めて考えてみても、結局は分からないと思うんです。
奥田:
なるほど。何かに夢中になるには、興味の他にどのような要素があるのでしょうか。
嘉糠:
私の言う「好き」は、自由意志ではなく、もしかしたら決定論に近いものかも知れません。病原体媒介節足動物への興味は、20年以上経っても未だに途切れることはなく、生まれつきの性向かな、とも思うからです。
ただ、大事なことがあって、自分が興味のあることとの出会い方、つまり「運と縁と機(機会)」です。仮に、私が子どもの時に病原体媒介節足動物のことを知ったとして、周りが見えないくらいに夢中になれたかというと、きっと違う。あるタイミングで、あるウィンドウで、夢中になれるものに出会うのがとても大切なのです。
人生の後半、例えば50歳ぐらいで病原体節足媒介動物の概念を知ったときに、実力があれば研究分野を移せるかもしれませんが、実際にはなかなか難しいでしょう。その点で、大学院生だったくらいの時分に、これだと思うものに巡り会えたのは幸運でした。
やりたいことができる場所を求めて
奥田:
大学院を修了して留学したのちに、東京大学を経てすぐに帯広畜産大学に異動したのはなぜですか。
嘉糠:
留学先から東大に移って、病原体を媒介する蚊の研究を始めようとしたところ、すったもんだの末、それを実施することは東大では出来ない、ということになったのです。当時は、分子生物学系の蚊のラボなら、ハマダラカやヤブカの遺伝子組換え個体を使って研究するのが当たり前でした。私もそのような研究をすべく所々申請したのですが、結局認められなかった。
これはまいったな、と思っていたところ、タイミングよく帯広畜産大学から声が掛かったのです。帯広畜産大学には、原虫病研究センターという、感染症研究に特化した組織があり、蚊やマダニなどの病原体媒介節足動物の研究もおこなわれていました。私は二つ返事で飛びつきました。
奥田:
そこで蚊についてのフィールドワークを始められたのですか。
嘉糠:
そうです。ただ、私の場合、それまでフィールドに関連する研究は全くやったことがなかったので、自分でイチからフィールドを開拓しないといけませんでした。どうしたものかと思案していたところ、ひょんなことから、そのきっかけが生まれることに。
アマゾンで開催された蚊の研究集会に参加した時に、西アフリカのブルキナファソの若手研究者と意気投合したのです。そこからトントン拍子に話が進み、ブルキナファソで共同研究を始めようということになりました。フランス語圏ということもあり、在留邦人がそもそも極めて少なく、ブルキナファソに飛び込んだ日本の感染症研究者は私が初めてでした。日常生活でのコミュニケーションは大変でしたが、現地の研究者からは予想以上に歓迎されました。
振り返ると、私のように研究分野を大きく変えた結果、人脈が全くない状態の人間が飛び込むには、良い国の選択だったと感じます。

私はあくまでも「虫」の研究者
奥田:
そもそも、フィールドワークをしようと思われたのはなぜでしょうか。
嘉糠:
私は、「患者」を治そう、もしくは「疾患」を撲滅しよう…と思って研究をしていません。もちろん、最終的に患者さんを救えることは理想ですが、医師でもない私は、直接その道筋に立っているわけではないのです。 私はあくまでも「虫」の研究者であり、虫を見て好奇心が湧く人間です。虫の生きざまを知りたい、それがフィールドワークを続けるうえでの一番のモチベーションです。
私の中では、病原体も一つの生き物だと捉えています。フィールドを眺めていると、「病原体」という生き物と「蚊」という生き物、そして「人間」という生き物が、ある意味で一つの「るつぼ」の中に共存しているように見えるのです。その関係性を見て、知りたいと思う、それこそが今でも変わらない私のフィールドワークの原動力です。
奥田:
研究のなかで、先生ご自身の「目的」というものはありますか。
嘉糠:
変な物言いですが、究極のところありません。
先ほどもお話ししましたが、私はただ「夢中になれるもの」を追いかけているだけなんです。
もともと家族からは医学部に行けと言われていましたが、自分が患者を治している姿がどうしても想像できなかった。きっと途中で飽きてしまうだろうと思い、結局医学部には進みませんでした。その感覚は今も変わっていません。西アフリカに行くと確かに多くの患者さんがいますが、彼らを救うのは自分のやるべきことではない。病気を治そう、制御しよう、と活動されている方々はたくさんいますから、私は違う立場で関われればいいと思っています。
そこは、自分の中でははっきりしています。
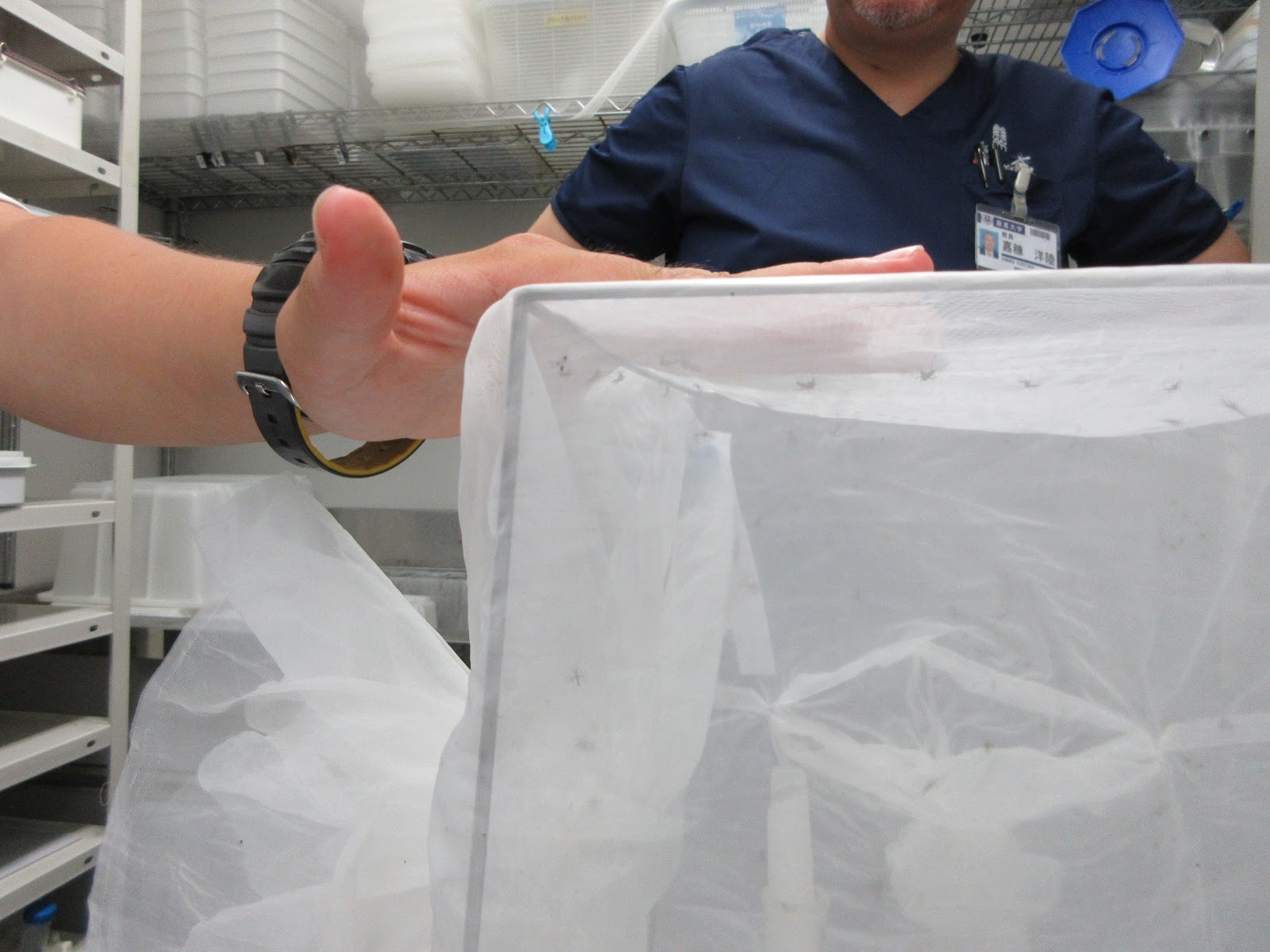
今後の目標
奥田:
先生の今後の目標や夢、やりたいことを教えてください。
嘉糠:
今一番興味を持っているのは、ある特徴を持った生き物を作ること、つまり「機能付加」です。昔から、生き物を作ることに興味がありました。高校生の時に、遺伝子やゲノムの概念を知って「4つの塩基を連結すれば何でもできる!」と思ったのが、バイオロジーに興味をもったきっかけです。裏を返すと、遺伝子を切り貼りすれば何でもできてしまうので、人工的な生き物も作れてしまうということですよね。
奥田:
なるほど。例えばどのような生き物でしょうか。
嘉糠:
ひとつは、蚊に刺されやすい、囮(おとり)になるような生き物を作ること。他人に比べて蚊に刺されやすい人が存在しますが、その理由は未だによく分かっていません。人間の体から出る、蚊を誘引する匂い物質は分かっているだけでも約200種類あります。この200種類から、最も蚊を引き寄せる匂い物質の組み合わせを見つけ出すのは、現実には不可能に近い。
一方で、哺乳類や鳥類で、刺されやすい生き物というのは確実に存在するのです。ゲノム編集などを活用して、遺伝的背景に介入することで、蚊に刺されやすい生き物を作りたいです。できれば、そのような生き物のベースとなるのは家畜が最適で、蚊媒介性感染症で困っている地域の人たちとwin-winになればいい、と夢想しています。
奥田:
遺伝子組み換え蚊を使って、マラリアやデング熱などを媒介する蚊の数を減らす試みも世の中にはありますが、先生はどうお考えですか。
嘉糠:
遺伝子組換えハマダラカやヤブカを用いて蚊の数を制御することは、一部は既に社会実装されています。公衆衛生の施策として取り込まれつつあるので、私のような人間が関わるフェーズはもう過ぎていると思っています。率直に言ってしまえば、誰かが先に進んでやっていることには、あまり興味が湧きません。
奥田:
研究者としては、やはり「自分が最初にやりたい」という思いがあるのでしょうか。
嘉糠:
どうでしょうね。シンプルに、他の人が既に手を付けていたら面白くない…ということに尽きると思います。だから私は、他の研究者が目も向けないような対象や事象を選ぶことが多いのです。
それに、他人がやっていない研究をする最大のメリットは、失敗しても誰にも怒られないことなんですよ(笑)。誰もやっていないから、「へえ、面白いね」で済んでしまう。そこが気楽で、楽しいところですね。
目の前の現象を大切に
奥田:
熱帯医学会員学生部会に向けてアドバイスやコメントをお願いします
嘉糠:
自分の目で見る「現象」を大事にしてください。ある現象を見て、自分の頭の中のアンテナがビビっと反応したら、それに食らいついてください。
ただ、その状態を経験するには、画面越しではダメです。自分の手を動かす、自分の足で向かう、そういう過程を経ないと本当の現象を身を持って体験することは叶いません。
目の前の患者の症状を見るのも、アフリカで蚊が沢山群がって飛んでいるのを見るのも、根っこは全て同じです。そういう現象を目の当たりにして、ピンと来るものがあったら、絶対に逃がさない。このことを若い人には意識してもらいたいのです。一方で、教え子の医学生から、たまに「患者や疾患に興味を持てない」という相談を受けることがあります。そんな時は、「興味を持てない」ということを肯定的に捉えるのが大切です。それは、自分が求めて焦がれる「現象」ではないという、ある種の啓示のようなものだからです。であれば、あらためて自分のアンテナを高く掲げ直して、好きなものを探し続けてみてください。

対談者プロフィール
嘉糠 洋陸
東京慈恵会医科大学・熱帯医学講座教授。山梨県甲府市出身。1997年東京大学農学部獣医学科卒業、2001年大阪大学大学院医学研究科修了、博士(医学)。理化学研究所で研究員をした後、米国スタンフォード大学で病原体節足媒介動物の研究を開始。帰国後、東京大学を経て、2005年に帯広畜産大学原虫病研究センター教授。2011年に東京慈恵会医科大学熱帯井医学講座教授。座右の銘は「好きこそものの上手なれ」。著書は「なぜ、蚊は人を襲うのか」(岩波科学ライブラリー)。
奥田 弥希
長崎大学医学部医学科3年。岡山県岡山市出身。中学生のときに国際保健に興味を持ち、その第一歩として長崎大学に進学。現在は熱帯医学研究所の細菌学分野にて研究に取り組んでいる。将来は感染症の専門家として臨床医と研究医の道を両立させたいと考えている。趣味は屋外レジャーでボート、登山、サイクリングなど。

