
研究で支える行動変容
重富:
現在、どのようなお仕事をされているのか教えてください。
凪:
教育と研究を実践しています。教育は、医学部医学科と看護学科に対する講義と実習、研究は、主にケニアで住血吸虫症や結核などの感染症に対する疫学研究を行っています。
重富:
現在のお仕事に至ったきっかけや背景を教えてください。
凪:
ケニアで日本人研究者と出会い、研究者としての道を示してくれたことが、私の職業選択に大きな影響を与えました。私は小さいころに事故で指を切断しましたが、手術によって指の喪失を免れることができた経験があります。その出来事について、「もしあのとき手術を受けられなかったら、私はどうなっていただろうか」と考えることがあり、年齢を重ねるにつれて、それを単なる幸運として片付けることはできなくなりました。こうした背景から、私は健康格差を減らすために自分自身が努力したいと思うようになり、JICA青年海外協力隊への参加や、大学編入学、ケニアでの公衆衛生大学院を経て博士課程へ進学しました。
現在は研究者という職業を選び、ケニアの大学院時代に出会えた仲間との共同研究を通じて、人々の健康改善につながる解決策を一緒に模索しています。その過程を楽しみながら、より地域社会の健康に役立つ方法を探し続けています。
重富:
ケニアでの大学院時代の交友関係が、現在の研究というお仕事にもつながっているのですね。先生は研究の強みはどこにあるとお考えですか。
凪:
疫学研究の重要な目的の1つは、結果から得られた科学的根拠(エビデンス)を政策につなげることです。つまり研究エビデンスを提示することは、自分たちが現地を去った後も人々の健康に寄与する方法でもあると言えます。私自身は健康教育とヘルスプロモーション領域にアプローチできる健康行動科学に強い関心があり、健康行動理論を基礎とした研究の立案や啓発・教育への応用を得意としています。特にケニアでの公衆衛生大学院時代には、ヘルスプロモーションを体系的に学ぶための専攻科を選択しました。このとき授業で使用していたテキストが、米国国立がん研究所(National Cancer Institute)出版の『Theory at a Glance : A Guide for Health Promotion Practice (Second Edition)』(編集:Karen Glanz,Barbara K.Rimer, 訳:福田吉治『一目でわかるヘルスプロモーション : 理論と実践ガイドブック』)でした。この冊子は、Glanzら編集の『Health Behavior: Theory, Research, and Practice (Fifth Edition)』(訳: 木原雅子・加治正行・木原正博)とあわせ羅針盤のような存在です。さらに現在では、日本における研究や実践事例が豊富にまとめられた良書『健康行動理論による研究と実践』(一般社団法人日本健康教育学会編)も刊行されており、誰もが健康という権利を享受できるように、種を蒔いてくれる先生方がいることを非常に心強く思っています。

協力隊経験が拓いた学びと挑戦
重富:
先生は保健学の学位を取得されていますが、どのようなバックグラウンドをお持ちなのですか。
凪:
保健学には看護学や診療放射線技術学などさまざまな分野がありますが、私はその中で臨床検査技術学を学びました。在学中に専門的な知識や技術を身につけるにつれて、医療資源が限られた地域でそれらを社会に役立てたいという思いが一層強まり、卒業後には青年海外協力隊への参加を決めていました。その後、モルディヴ共和国で協力隊員として活動した経験を経て大学に編入し、保健学の学位を取得しました。
重富:
現地ではどのような活動をされたのですか。
凪:
私が活動していた当時、モルディヴは臨床検査技師が不足しており、特に地方の病院では海外の人材に検査業務を依存している状況でした。そこで赴任先の病院長にお願いして現地スタッフを週に3回ほど配属してもらい、検査方法や手技の訓練を行いました。また、それらをまとめた英語の教材を作成し試験を実施することで、私も含め海外人材がいなくなった後も現地スタッフだけで検査を続けられる体制を整えました。この経験を通じて、 現場の課題を理解しつつ、持続可能な解決策を考える姿勢が身についたと感じています。
重富:
現地に行かれてからお考えなど変わったことはありますか。
凪:
これまでに学んだことを役立てたいという思いで協力隊に参加しましたが、実際に現地では、自分が学ぶことのほうがはるかに多く、当時の考えがいかに烏滸がましかったかを痛感しました。帰国後に4年制大学へ編入する決断をしたのも、この協力隊での経験が大きなきっかけとなっています。

ボトムアップ活動から研究へ
重富:
ケニアの大学院では、どのような1日を過ごしていたのですか。
凪:
大学院1年目は授業が多く、レポートや試験に追われる目まぐるしい毎日でした。
一方で2年目は研究の調査期間に入り、自分でスケジュールを柔軟に組めるようになりました。その頃、JICA(独立行政法人 国際協力機構)の能力強化研修で出会った仲間からNGO「少年ケニヤの友」のスタッフ募集を紹介してもらい、研究と仕事を両立する機会に恵まれました。学びを実践に結びつけ試行錯誤しながら過ごせた時間は非常に充実しており、プロジェクトを支えてこられた多くの方々に心から感謝しています。
重富:
その後はどのようなご活動をされたのですか。
凪:
ケニアの保健マネジメント強化プロジェクトに、当時チーフアドバイザーとして着任されていた杉下智彦先生にお声がけいただき、キャパシティビルディングアドバイザーとして約1年間プロジェクトでお世話になりました。
その中で特に貴重だったのは、保健行政官向けの研修や地方病院・コミュニティへの訪問を通じて、それぞれの現場の声を直接聞けた経験です。実際に地域で直面している課題を知ることで、ボトムアップだけでは解決が難しく、トップダウンの仕組みも組み合わせてこそ前進できるのだと、強い実感をもって学ぶことができました。
重富:
研究分野として国際保健に携わろうと思われたのは、そのときのご経験が影響しているのでしょうか。
凪:
そうですね。それもありますが、協力隊に参加したときに出会えた方の影響が大きかったです。友人はザンビアでマラリアに罹って亡くなってしまい、その現実はあまりに受け止めがたいものでした。しかし、この事実を受け入れ向き合う過程が、感染症について研究する道を選ぶ大きな動機になったのだと思います。
重富:
そうだったのですね。
専門分野の定め方
重富:
私も専攻が保健学なので、医師以外のコメディカルとしての関わり方について先生のお考えを伺いたいです。
凪:
一人の健康を支えるためには、医師以外にもさまざまな役割があります。大切なことは、自分自身の強みが活かせる分野を見つけることではないかと思います。
重富:
自身の強みの分野を見つけていくというのは、私が今まさに悩んでいるところです。
凪:
その気持ち、私も悩んだので理解できます。これまで学んできた保健学の知識や技術を土台にしつつ、自分が最も重視したいことを軸に専門分野を選ぶのも一つの方法です。自分が得意だと思えることや、やっていて楽しいと感じられる分野があれば、そこに進めば良いのではないでしょうか。
重富:
少し大きな問いになりますが、日本人が国際保健に関わる意義について、先生はどのようにお考えですか。
凪:
私自身は「日本人が」と特別に意識して考えたことはあまりありません。むしろ、「これをやってみたい」とか「自分の力を活かせるかもしれない」と感じる人が関われば良いと思っています。大切なのは国籍ではなく、目標を持ち、その目標に向って必要なことを実行できるかどうかだと思います。ですから、日本人だからという理由で特別に意義を見出す必要はないのではないでしょうか。
重富:
たしかにお話を伺って、国際保健に関わるうえで国籍そのものは大きな意味を持たないのだと感じました。
ケニアでの挑戦と行動を起こすきっかけづくり
重富:
先生の今後の目標はなんですか。
凪:
研究だけでなく、地域の人たちと一緒に前へ進める活動に発展させていくことを目指しています。これまでケニアで取り組んできた疫学研究では、対象地域の住民を調査員として育成し、研究目的に沿った質問紙調査を行ってきました。最近では、その中に大学や専門学校を卒業した若者も増え、地域にとって貴重な人材になっていると感じています。ただ、そうした若者たちが地域で力を発揮できる機会は、まだ限られているのが現状です。そこで今はケニアの大学院時代の仲間や旧友と協力して、地域の人材が活躍できる場を広げるための人材登録を基盤としたプラットホームづくりを進めています。
特に研究では、人とのつながりともいわれるソーシャルキャピタル(社会的資本)を公衆衛生対策に活かすための基盤づくりに取り組んでいます。例えば私たちの研究では、調査地域の子どもを対象に感染予防教育を行い、その子どもが習得した知識や行動が周囲の人々に広がるか、いわゆるスピルオーバー効果を生みだすかの検証を目的の一つとしています。こうした取り組みを通じて、教育効果に影響する要因を明らかにし、得られた知見を効果的に共有・活用できる仕組みを整えることで、人々を取り巻く社会環境の改善につなげたいと考えています。またその一助として、調査員研修を受けた人々のネットワークが広がり、地域全体のヘルスリテラシーの向上に寄与することを期待しています。
重富:
先生から学生へのアドバイスがあれば伺いたいです。
凪:
さまざまな考え方や価値観に触れることが大切だと思います。
生きていくなかで、誰もが忘れがたい思い出や、心を揺さぶられる経験を持っていると思います。そうした自分の心を突き動かすような経験や感情を共有し、客観的に自分自身と向き合う機会を持つことが、成長のきっかけになるのではないでしょうか。
また、人や本との出会いを通じて、新たな考え方や視点を知ることも大事だと思います。自分が間違った方向に進みかけたときに、「それは違うんじゃない?」とか「こうしたほうがいいよ」と助言や気づきを与えてくれる存在はとても貴重です。そうした言葉を素直に受けとめ、必要に応じて軌道修正できる柔軟さを身につけることが、よりよい人生の方向づけには欠かせないと思います。
重富:
本当に多くの学びをいただきました。ありがとうございました。
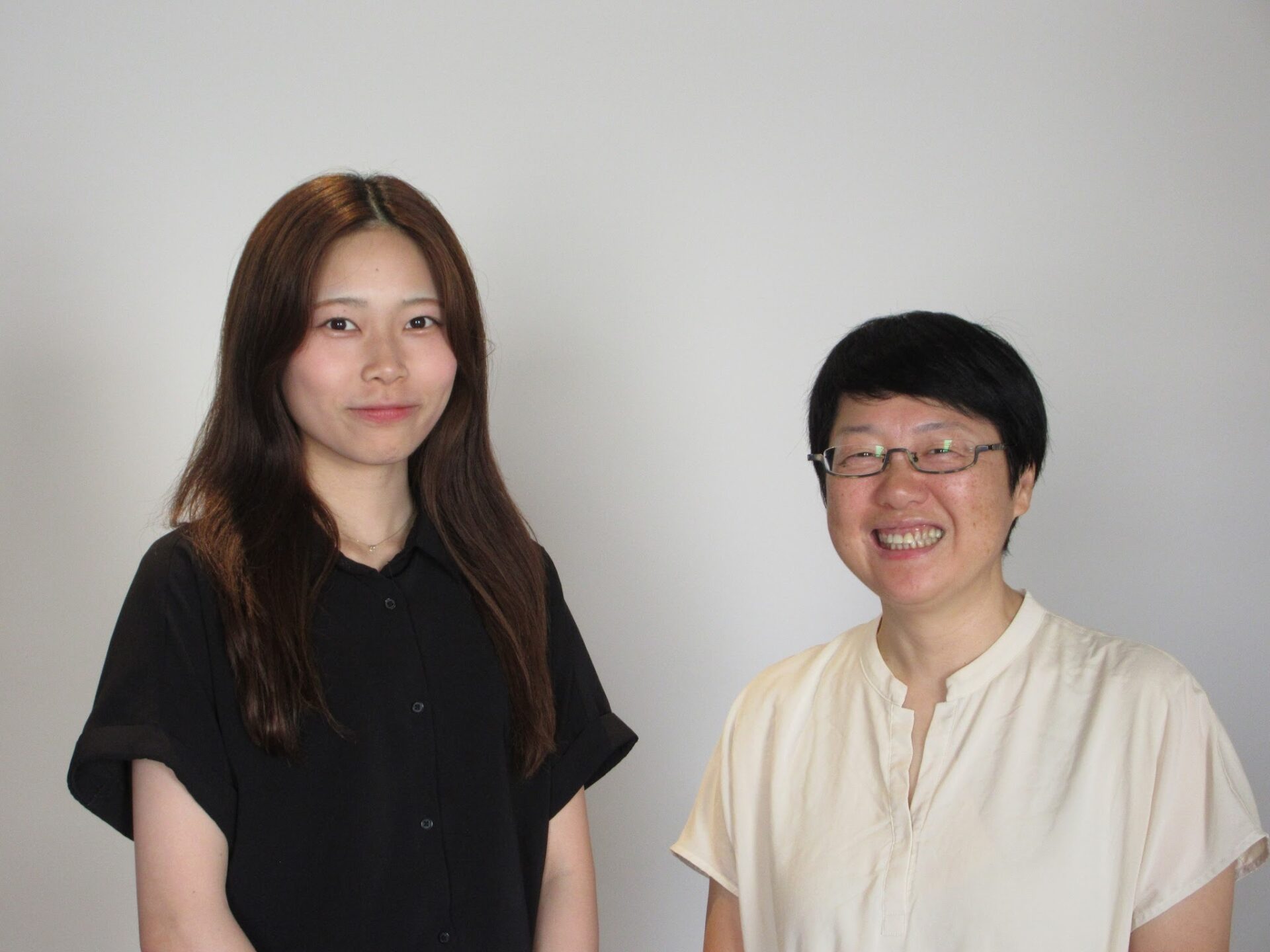
対談者プロフィール
凪 幸世
東京女子医科大学医学部医学科 衛生学公衆衛生学講座(グローバルヘルス部門)、助教。JICA青年海外協力隊員としてモルディヴ共和国に赴任後、岡山大学医学部保健学科(検査技術科学専攻)に編入学。国際NGOケニアFamily Health International (FHI)に参画後、公衆衛生学修士号をケニアのモイ大学にて取得。長崎大学大学院医歯薬学総合研究科(新興感染症病態制御学系専攻)にて博士(医学)を取得後、久留米大学医学部医学科 公衆衛生学講座を経て現職。趣味は、登山と陶芸、好きな本はWilliam Osler著「Aquanimitus(平静の心)」
重富 千春
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 保健学専攻 保健師養成コース1年。福岡県出身。2025年に同大学保健学科(看護学専攻)卒業。将来は保健師として国際保健分野で活躍することを目指す。興味分野は「顧みられない熱帯病(NTDs)」「WASH」。趣味は美術館へ行くこと。

